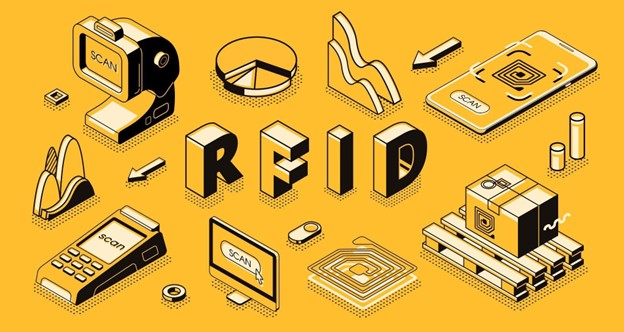
近年、工場や物流現場を中心にRFIDを活用する事例が急速に広がっています。非接触でモノや人の識別ができるRFIDは、業務効率化やセキュリティ強化を求める企業にとって注目の技術です。
RFID導入が進む背景には、人手不足や業務の属人化といった課題があります。RFIDによって情報をリアルタイムに把握できるようになれば、工数削減だけでなく、経営判断の迅速化にもつながります。
本記事では、RFIDの仕組みから実際の活用事例、導入によるメリットまでを丁寧に解説します。
RFIDとは?その仕組みと特徴

RFID(Radio Frequency Identification)とは、RFIDタグに記録されたID情報を電波で読み取る技術です。タグを貼り付けた物品や、タグを身に着けた人を非接触で識別・記録でき、複数の対象を同時に読み取ることも可能です。
「タグ」「リーダー」「アンテナ」の3つで構成され、バーコードのように1点ずつスキャンする必要がなく、タグが見える位置にある必要もありません。読み取り距離は数センチから数メートルまで対応し、アンテナの近くを通るだけで自動的に認識されます。ハンディタイプのリーダーを使えば、棚卸しや検品などにも柔軟に対応でき、現場の作業を大幅に高速化できます。
以下で、「タグの種類(電源方式別)」と「周波数帯と主な用途」を表で整理し、具体的な特徴を解説します。
タグの種類(電源方式別)
| タグの種別 | 電源 | 読取距離※ | 想定コスト(目安) |
|---|---|---|---|
| パッシブタグ | 不要(リーダーの電波で応答) | 1~10m | 数円~数十円/枚 |
| アクティブタグ | 電池内蔵(自ら発信) | 50m以上 | 数百~数千円/個 |
パッシブタグはリーダーから送られてくる電波を受け取って応答する仕組みのため電池が不要です。電池が不要なため価格がきわめて安価で、シール状やカード状など軽量な形態に加工しやすく、商品ラベルやケース管理など「大量に貼り付けて使い捨てる」用途に適しています。
一方、アクティブタグは電池を内蔵して自ら電波を発信できるため、数十メートル以上の長距離通信が可能です。さらに温度・振動・位置情報といった各種センサーを組み込めることから、高価でも資産トラッキングや車両の動態管理など「遠距離から状態まで把握したい」シーンで採用されることが多くなっています。
周波数帯と主な用途
| 周波数帯 | 読取距離 | 主な国内用途 |
|---|---|---|
| LF(125kHz) | 数cm | 動物個体識別、車のイモビライザー |
| HF(13.56MHz) | 数十cm | 交通系ICカード、社員証 |
| UHF(920MHz) | 数m | 物流ゲート、工場の車両入退場管理 |
とくにUHF帯パッシブタグは、物流センターや工場敷地で「車両を止めずにゲートを通過させる」用途に広く使われています。LFとHFは通信距離が短い分、金属や水分の影響を受けにくく、近距離認証や電子マネーなど精度重視のシーンで重宝されています。
【業界・業務別】RFIDの活用事例

ここでは、実際にRFIDの導入事例をもとに、業界別の活用シーンをご紹介します。
製造業の事例:守衛業務の省力化と入退場の自動化
- 車両通過量:500台/日
- 運用体制:24時間365日
- 管理対象:車両+人
社員通勤と搬送車両が重なり渋滞が常態化していた電機メーカー工場。RFID通行証を使ったノンストップゲートに切り替えたことで、守衛はモニター監視中心の少人数体制へ移行し、動線整理とセキュリティ向上を両立しました。
物流業の事例:在庫管理とピッキング精度向上
- 管理対象:パレット・通い箱・フォークリフト
- 導入範囲:入出庫ゲート/倉庫内動線
- 読取方式:UHFタグ+固定リーダー/ハンディリーダー
入出庫時は大量のアイテムを一括で読み取り、確認漏れを防止。人やフォークリフトの動線データを蓄積し、レイアウト改善や事故防止に活用しています。
医療業界の事例:医薬品サプライチェーン・トレーサビリティ
- 管理対象:RFID タグ付きボトル・薬液バッグ・錠剤シート
- 導入範囲:製薬メーカー/卸/病院・調剤薬局
- 読取方式:UHFタグ+固定リーダー
製造から調剤まで医薬品を個品単位で追跡し、偽造品チェックと入出荷業務の正確化・省力化を実現しました。
建設業の事例:資材・工具のリアルタイム管理
- 管理対象:工具・配管資材など数千点規模/日
- 導入範囲:資材ヤード/仮設ゲート
- 読取方式:UHFタグ+固定リーダー
持出・返却を自動記録し所在を即時追跡。紛失や探し物を抑制し、作業効率と資材セキュリティを両立しました。
食品・医療施設の事例:フードディフェンス対応と履歴管理
- 導入目的:車両入退履歴の厳格化
- 管理対象:加工原料・医療資材の搬入車両
食品原材料メーカーでは、HACCP対応の一環として車両入退履歴を自動保存。RFIDによる非接触記録で監査準備の工数を削減し、フードディフェンス体制を強化しています。
RFID導入のメリットと将来の展望

RFIDを導入するメリットは、単なる業務効率化にとどまらず、企業のDX推進や経営基盤の強化にもつながる点にあります。
以下に、導入によって得られる主なメリットを整理しました。
1. 業務の自動化・省人化
- 記帳や目視確認をなくし、少人数でも現場を運営できる。
- データ共有で属人化を排除し、協力会社との手続きを効率化できる。
2. 在庫管理・棚卸の高速化
- 一括読取で棚卸時間を大幅に短縮できる。
- 工具や医療機器の所在を即時検索し、紛失リスクを低減できる。
3. 製造トレーサビリティ&物流追跡
- 仕掛品や治具をリアルタイムで追跡し、滞留工程を可視化できる。
- 出荷から配送までのステータスを自動連携し、誤配送を防止できる。
4. リアルタイムデータ化&セキュリティ強化
- 人・車両・資産の動きを即時に記録し、基幹システムへ連携できる。
- 不正侵入や持ち出しを検知し、事故発生時の追跡を容易にできる。
5. 決済&監査対応
- 商品をまとめて精算し、待ち時間をゼロにできる。
- 履歴を自動保存し、内部統制や外部監査の対応を簡便化できる。
今後、RFIDはスマートファクトリーやスマートオフィスといった概念の中核を担う技術へと進化していくでしょう。たとえば、製造ラインとRFIDを連動させてリアルタイムで品質をチェックしたり、従業員の入退記録と勤怠管理システムを一元化したりといった活用が現実のものになりつつあります。
また、社内資産の所在管理や備品の棚卸といった日常業務にもRFIDは応用され始めています。特に複数拠点を持つ大企業においては、「どこに何があるのか」「いつ使われたのか」を可視化することが、リスク管理とコスト最適化のポイントです。今後のビジネスにおいて、その重要性はますます高まっていくでしょう。
西部電気工業のRFID活用事例「すいすい入退+」

西部電気工業株式会社が提供する「すいすい入退+」は、RFID技術を活用した入退管理システムです。複数のセンサーやネットワーク機器を組み合わせ、人物や車両の入退場を自動で認識・記録することで、セキュリティと業務効率の両立を実現しています。
このシステムは、身につけたRFIDタグとゲートのセンサーが連動し、登録された車両は停止することなくスムーズに通過できます。守衛がいちいち記帳や目視確認を行う必要がなくなり、24時間体制での運用も可能になります。
特に注目すべきは、RFIDだけでなく、既存のナンバープレート認証システムやパトライトによる可視化、リアルタイムな入退状況の把握といった機能とも、カスタマイズによって柔軟に連携できる点です。これにより、管理者は守衛室から遠隔で状況を確認でき、現場の負担を最小限に抑えた形で、セキュリティの維持が可能となります。
実際に、ある大規模工場や物流施設などでは「すいすい入退+」の導入によって、以下のような効果が得られています。
- 守衛業務の人員削減
- 車両渋滞の解消
- 不正侵入の防止
- 履歴データの自動蓄積と活用
これらの成果から、「すいすい入退+」は単なるゲート自動化にとどまらず、企業のDX推進にも寄与するツールとして評価いただいています。
「すいすい入退+」の詳細については、西部電気工業公式サイトのソリューション紹介ページもご参照ください。
RFIDの活用事例と企業における導入メリットとは?:まとめ

RFIDは、単に現場業務の効率化を図る技術ではありません。人手不足や業務属人化、セキュリティの課題に悩むBtoB企業にとって、経営基盤を支える技術とも言える存在です。製造、物流、医療、建設など、さまざまな業界での導入事例を見ても、その汎用性と効果は明らかでしょう。
西部電気工業では、こうしたRFIDの多様な自動認識手段を活かし、工場の治具や製品、部品などの所在管理から、人や車の入退管理に至るまで、幅広いソリューションを展開しています。特に、入退管理システム「すいすい入退+」は、セキュリティと業務効率の向上を両立させたい企業のニーズに応える製品として、高い評価をいただいています。
RFIDの導入を検討中の方は、ぜひ西部電気工業にご相談ください。「自動認識基本技術者」や「RFID専門技術者」が、貴社の業務課題や施設環境に応じた、最適なシステム構成をご提案いたします。

