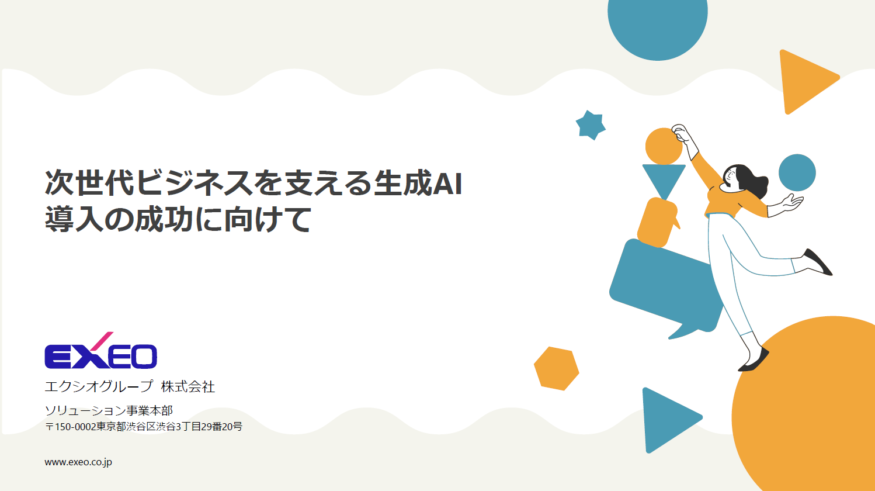ChatGPTをはじめとした生成AIの急速な進化により、多くの企業への導入ニーズが高まっています。ビジネス文書の自動生成や新規事業のアイデア出しなど幅広い業務への活用が期待される一方で、「導入してみたものの活かしきれない」「情報漏えいが心配」「どこから始めるべきか分からない」といった課題を感じている企業も少なくありません。
本記事では、企業が生成AIを導入する際に直面しがちな5つの課題と、それぞれに対する具体的な解決策をセットでご紹介します。
生成AIの導入が注目されているのはなぜ?
2022年末に登場したChatGPTを皮切りに、GoogleのGeminiやAnthropicのClaudeなど、生成AIの進化が加速しています。これまでAIといえば、大量のデータ分析を得意とする技術として認識されていましたが、生成AIの登場によって人の思考を支援するツールへと進化。その結果、企業におけるAIの活用範囲が飛躍的に広がりました。
特に代表的な生成AIの用途には以下のようなものが挙げられます。
- 営業メールや企画書の下書き生成
- 議事録の要約
- 報告書の自動作成
- よくある質問の自動応答
- マニュアル作成
- FAQデータベースの構築
- プログラミング支援(コーディング・デバッグなど)
これらはすでに一部の企業で実績を上げており、人的リソースの不足や業務の属人化の解消、情報共有の効率化といった効果も現れ始めています。
また、社内のナレッジをAIに学習させることで、社内ポータルや社内ヘルプデスクのような用途にも応用できるため、業種を問わず導入を検討する企業が増えているのです。
生成AIの導入における主な5つの課題
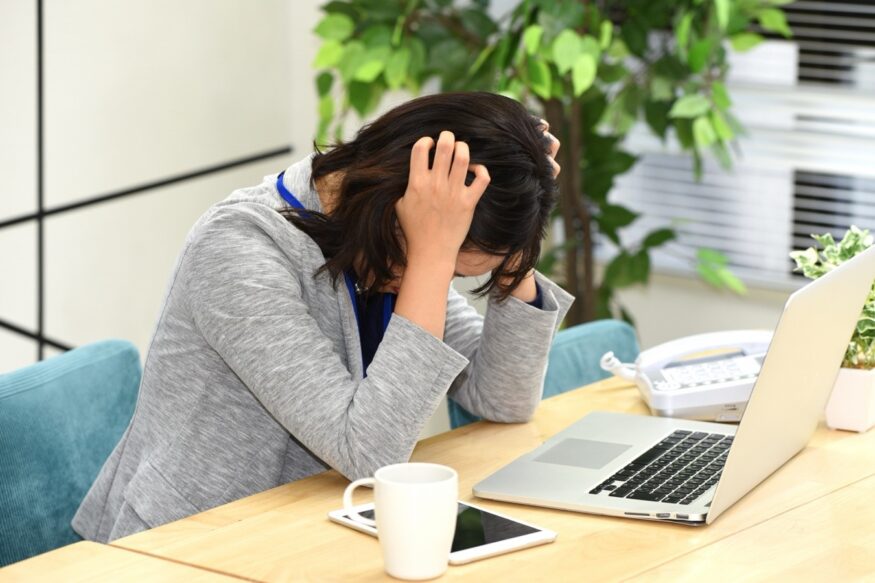
生成AIを導入したからといってすぐに成果が出るわけではありません。現場レベルではさまざまなハードルに直面し、生成AIというツールが定着せず活用が進まないケースも多く見られます。
企業によっても生成AIの導入における課題はさまざまですが、今回は特に代表的な5つのパターンに分けてご紹介します。
1. 導入の目的が不明確
多くの企業が抱える最初のつまずきが、「生成AIを導入したものの、どういった業務・作業に活用するのかが定まっていない」という課題です。生成AIは文章生成や要約、翻訳、アイデア出しなど幅広い用途がありますが、汎用性が高いからこそ導入の目的を見失いやすいともいえます。
「とりあえずChatGPTを社員に使わせてみたが、使い道が定着しない」「どの部署も自由に使っているが成果が見えない」といった声は実際の導入現場でも多く聞かれます。目的や業務が不明確だと使われないまま自然消滅してしまうことも珍しくありません。
2. 社内のリテラシー・スキルの不足
生成AIのパフォーマンスを引き出し現場で活用していくためには、ツールを使う側の社員にも一定のリテラシーやスキルが求められます。
たとえば、「◯月◯週の売上データをもとに報告書を作成して」という単純なプロンプト(指示文)を入力しただけでは、グラフや図表のない文章だけのわかりにくい内容になってしまったり、具体的な原因や改善策のないありきたりな報告書に仕上がったりすることもあります。期待通りの内容を出力するためには、適切なプロンプトの作成が求められるのです。
ところが、ITスキルや情報感度の高い一部の社員のみに生成AIの利用が偏ってしまうと社内全体での利活用が進みません。さらに、「プロンプトの書き方が分からない」「使い方を人に聞きづらい」といった社員の心理的なハードルも大きな課題であり、さらに社内のリテラシー格差が拡大していく要因にもなりかねません。
3. セキュリティ対策・情報漏えいの懸念
多くの生成AIはインターネット経由で情報を送受信しており、入力された内容は学習データとして蓄積されていきます。このような基本的な特性について社内の理解が不足していると、機密情報や個人情報をうっかり入力してしまい、重大な情報漏えいにつながるリスクがあります。
たとえば、営業提案資料や顧客情報、開発中の製品情報など、企業にとって重要な知的財産がAIに渡る可能性があるため慎重な運用が求められます。また、法令や社内規定との整合性も確認しなければならず、IT部門・法務部門との連携も欠かせません。
4. 社内システムとの連携ハードル
生成AIは単体では便利でも、既存の業務ツールやシステムと連携できなければ使いどころが限られてしまいます。たとえば、議事録の要約が自動生成できたとしても、それが社内の情報共有ツールと連携していなければ手作業でコピー&ペーストする必要があり、結局手間が増えるという本末転倒な事態に陥ることも。
また、社内システムの仕様によっては、API連携やワークフロー自動化など高度な技術的対応が必要になる場面も多く、IT部門の負担やスキル不足も導入の障壁となっています。実際に、「現場では使いたがっているが、既存のシステムとつながらないから導入が進まない」という声は少なくないのです。
課題を乗り越えるための具体的な解決策5選

生成AI導入にあたってはさまざまな課題がありますが、これらを乗り越えるためにはどういった解決法があるのでしょうか。
1. 導入目的を明確化する
生成AIの導入に向けて最初に行うべきなのは目的の明確化です。業務効率化や生産性の向上、コストの削減、人手不足への対応など、企業が抱えている課題はさまざまですが、現場が困っていることと生成AIの接点を明確にすると導入目的が見えてくることもあります。
たとえば、議事録の作成やメールチェックに時間を要している場合には、生成AIに内容を要約してもらうことで工数の削減が期待できるでしょう。また、営業活動に欠かせない提案書の作成にも多くの時間を要しがちですが、生成AIを活用したたき台を作成できれば、それをもとにさらにブラッシュアップし精度を高めることもできます。
2. 社内教育とテンプレートの整備
リテラシーの格差を解消するには、個人のスキルに依存しない仕組みづくりが重要です。社内で利用頻度の高い作業については、あらかじめパターンをテンプレート化しておき、誰でもすぐに使える状態を目指しましょう。
たとえば、メールの要約や議事録の作成など、多くの部署で共通して使用できるプロンプトは一覧にまとめて全社に展開したり、プロンプトの書き方を学べる勉強会を社内で実施するなどの対策が有効です。
また、部署ごとに生成AIの活用成功事例をまとめて共有することも、現場の理解を広げる助けになります。
3. 情報管理のルールと運用ポリシーの策定
セキュリティの不安を払拭するには、生成AIに入力してはいけないものを明確にし、社員が安心して使える環境を整える必要があります。
たとえば、「個人情報・未発表資料は入力NG」など具体的なルールを策定したうえで、それらを踏まえた生成AI利用に関するガイドラインを作成し全社に展開しておくのもひとつの方法です。
また、一般的に利用されているクラウドサービス型の生成AIではなく、オンプレミスや社内閉域型のAIシステムの導入も検討してみましょう。
4. 小さな業務から段階的に組み込む
社内システムとの連携にハードルを感じている場合には、まずは既存のツールに組み込める範囲から試すのがポイントです。
たとえば、SlackやTeamsとChatGPTを連携させ、顧客や社員からの定型質問の応答に活用してみたり、Googleドキュメントの音声入力機能とChatGPTで議事録作成を半自動化したりと、さまざまな用途が考えられます。
身近な業務に対して自然に導入することが生成AIを定着させる鍵となり、そこからさまざまな用途に活用アイデアが広がっていきます。
5. KPIの設定と活用ログの可視化
生成AIを導入した結果、現場では多くの社員がその利便性を体感できたとしても、どういった効果が見込めるのかを定量的に可視化できなければ経営層の理解や予算の獲得は困難です。生成AIを導入して、単に「便利だった」で終わらせないためには数字による裏付けが必要です。
たとえば、メールチェックや議事録の作成に要していた時間がどの程度削減できたのか、生成AIの月間使用回数や利用部署の増加数、ドキュメント作成の自動化による工数の削減量などのKPIを設定し、導入前と導入後のデータを収集してみましょう。
これらを定期的に社内報やミーティングで共有することで、「生成AIが成果を出している」という実感が社内に広がりやすくなります。
生成AIの導入に失敗しないためのポイント
生成AIの導入は単にツールを導入して終わりではありません。「どのように社内に定着させ、効果を広げていくか」までを見据えた設計が必要です。
生成AIの導入と活用を成功に導くために企業が意識すべき3つの実践的なポイントをご紹介します。
1. スモールスタートを徹底する
生成AIに限らず、いきなり全社を対象としてシステムを導入しようとすると、現場の業務に支障をきたし混乱や反発を招くリスクがあります。そこで、最初の段階では小規模なチームや部署を対象に試験導入し、具体的な成果や課題を把握することが重要です。
成功例を1つでも作ることで社内における説得材料になり、横展開もしやすくなります。
2. 現場ニーズに寄り添う
生成AIを導入する際は現場の声や業務プロセスを無視せず、現実的な活用方法を見つけることが成功のカギとなります。
たとえば、“AIファースト”を過剰に意識するあまり、既存の業務プロセスが大幅に改変されるとなると現場の負担が増加し本末転倒の結果になりかねません。IT部門や経営層だけで方針を決めず、実際にツールを使う社員やチームの声を丁寧に吸い上げることが重要です。
3. ガイドラインと教育体制をセットで整える
情報セキュリティへの不安から、「怖くて使えない」「何がOKか分からない」という状況に陥りやすいのが生成AIです。そこで重要なのが、社内向けのガイドラインと教育体制の整備です。
ガイドラインには基本的な生成AIの使い方やプロンプト例はもちろん、入力すべきではない情報(個人情報や機密情報の一例など)も具体的に記載しておきましょう。
また、ガイドラインに沿って生成AIの使い方をレクチャーする研修や勉強会も実施することで社内での活用が広がっていきます。
生成AIの導入成功には計画的な設計と運用がカギ
生成AIは単なる業務効率化ツールにとどまらず、企業の働き方や情報共有のあり方そのものを変えられる可能性を秘めています。しかし、それを十分に引き出すためには、課題を正しく理解し計画的に導入・運用していくことが求められます。
導入を成功させるには、まず明確な生成AI活用の目的を設定し、現場に寄り添った設計と段階的な導入が重要です。その上で、リテラシー格差やセキュリティ面の不安を解消するための教育やルール整備も求められるでしょう。
「うまく使いこなせないかもしれない」という不安があっても、まずはスモールスタートを心がけ、小さな成功を積み重ねていくことが大きな成果につながります。
生成AIの導入はゴールではなく、企業の成長を支えるための手段に過ぎません。未来の働き方を見据え、今から着実に準備を進めていきましょう。