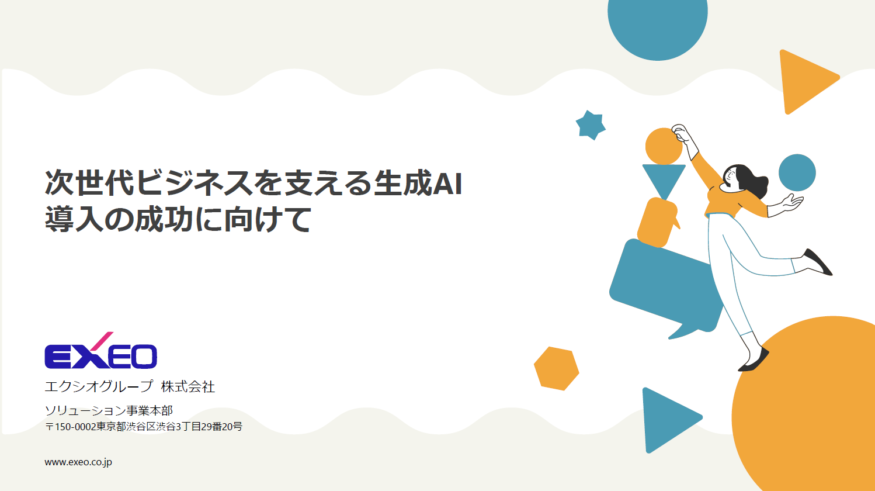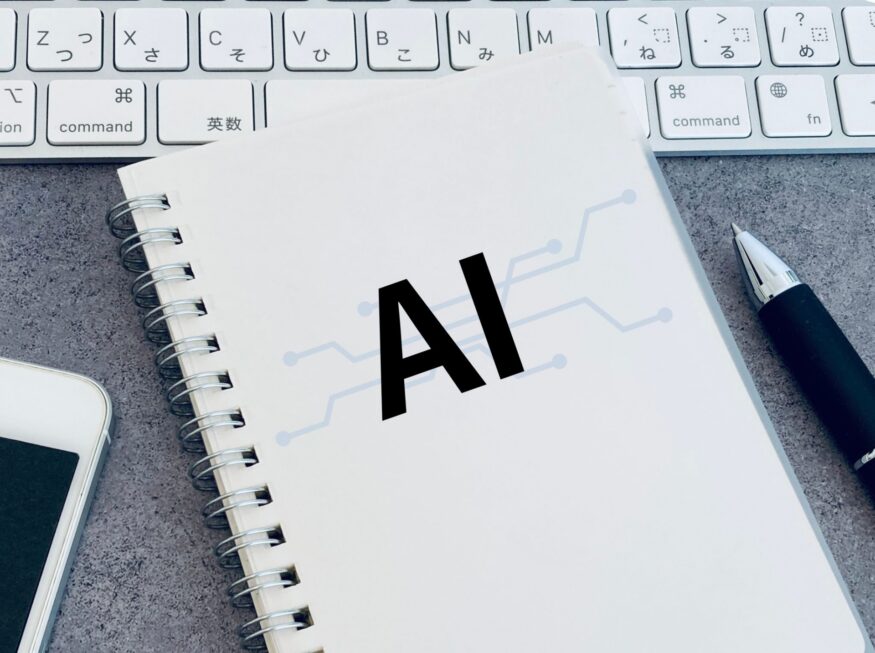
企業や組織におけるデータ分析の重要性が高まる中、生成AIによるデータ活用が注目されています。生成AIには多くのメリットがありますが、その効果を最大限に引き出すためには、適切な使い方や、生成AIでデータ活用する際の特性を理解しておくことが重要です。
この記事では、生成AIでできるデータ活用の内容やメリット、具体的な分析・加工の方法、注意点、無料で使えるツール、実際の活用事例についてわかりやすく解説します。
生成AIによるデータ活用とは
生成AI(Generative AI)は、学習したデータに基づき、テキスト・画像・音声・動画・コードなどを新たに作り出す人工知能です。生成AIを活用したデータ分析とは、AIが膨大なデータを要約・分類・分析し、業務の効率化や意思決定を支援する手法です。
従来の手作業によるデータ分析と異なり、自然言語による操作が可能なため、専門的なスキルがなくても直感的に扱えます。
生成AIのデータ活用でできること
生成AIは、従来のデータ分析では難しかった自然言語処理やパターン抽出を得意とし、多様なビジネス課題に対応できるツールとして注目されています。ここでは、生成AIのデータ活用でできることと、それらの仕組みについて解説します。
自然言語でのデータクエリ
生成AIは、人が話すような自然な言葉を理解し、クエリ(要求)に応じたデータ処理を実行します。例えば、「今年の月別売上をグラフにして」といった曖昧な指示に対しても、背後で意図を解釈し、必要な集計・可視化処理を自動で実行することが可能です。
これは、大規模言語モデル(LLM)の自然言語理解能力と、構造化データを扱うツールとの連携によって実現されています。
大量データの要約
生成AIは、大量のテキストデータを短くまとめて表現する能力に優れています。そのため、複数ページにわたる調査レポートや議事録、SNSの投稿など、従来は目視での確認が必要だった情報も、AIであれば数行のテキストに圧縮して提示することが可能です。
これは、トークン(テキストデータを処理する際の最小単位)ごとの重要度を判断しながら文脈を維持するという、生成AIの高度な文書理解能力によるものです。
異常検知・傾向分析
生成AIは、異常検知や傾向の可視化といった分析にも役立ちます。例えば、製造設備やインフラ、車両などに設置されたセンサーが収集するIoTデータや、店舗・ECサイトの売上履歴といった時系列データを分析し、異常値の検出やパターンを可視化することが可能です。
このような分析には、「教師なし学習(正解データを用いずにデータのパターンや構造を見つけ出す機械学習の手法)」や、「統計的モデリング(確率分布を用いて現象の理解と予測を行う数理モデル)」が用いられています。
さらに、生成AIならではの自然言語による説明機能を組み合わせ、専門的な分析結果についても、「どの部分に異常があるのか」「なぜ異常と判断されたのか」などの説明をわかりやすく提示します。
顧客データに基づくコンテンツ自動生成
生成AIでは、顧客の属性や購買履歴などのデータをもとに、個別に最適化されたメール文や広告文を自動生成することが可能です。
データに基づくコンテンツの自動生成は、事前学習済みの言語モデルや、個別データを組み合わせて応答を調整する仕組み(RAGやプロンプト設計)によって実現されます。
ユーザーレビューの感情分析
生成AIは、ユーザーから寄せられたレビューやSNSのコメントを読み取り、ポジティブ・ネガティブといった感情の分類も行えます。
このような処理は、文脈理解と感情語の識別に長けた言語モデルが、文中のトーンや言い回しから感情傾向を抽出する仕組みによるものです。
プロダクト改善点の抽出
顧客サポート履歴やフィードバックコメントなどから、製品やサービスの改善点を抽出することも、生成AIの得意領域です。自然言語で書かれた大量の意見の中から、「どの点に不満が多いか」「どの機能に繰り返し要望があるか」を体系的に可視化できます。
改善点の抽出は、類似表現のグルーピングや頻出パターンの抽出による構造化処理によって行われています。
競合分析の自動化
他社のWebサイトやSNS投稿、ニュースなどを生成AIに読み込ませることで、競合企業の特徴や最新の動向を自動で整理・分析することも可能です。
特に、決まった形式を持たないテキスト・画像・音声・動画などの「非構造化データ」をもとにキーワードやトレンドを抽出し、要点を自然言語で要約できるのは、生成AIならではの能力といえるでしょう。
生成AIによるデータ活用のメリット

生成AIによるデータ活用は、これまで人手や専門知識を要していた作業を自動化・効率化し、より直感的かつ迅速にビジネスに活かせる形で情報を引き出すことを可能にします。ここでは、企業が生成AIを取り入れることで得られる主なメリットを4つ見ていきましょう。
データ分析を効率化・自動化できる
従来のデータ分析は、専門のデータサイエンティストが行う必要があり、集計・加工・可視化までに多くの時間とコストがかかっていました。一方で生成AIの場合、自然言語の指示でこれらの工程を一括で実行できるため、非エンジニアでも分析を行えるようになります。
例えば、「売上データから月別の伸び率をグラフ化して」などの指示を与えるだけで、AIが自動で処理・出力します。これにより、現場担当者が素早く仮説を検証し、判断材料とすることが可能です。
データに基づいた意思決定が可能に
生成AIは大量の情報を瞬時に整理し、要点を抽出する能力に優れているため、ビジネス判断に必要な材料を短時間で提示できます。具体的には、経営会議に向けたレポート作成や市場トレンドの要約などもAIに任せることで、担当者は本来注力すべき意思決定に集中できるでしょう。
さらに、AIが異常値や例外パターンも自動検出するため、リスクの見落とし防止にもつながります。
製品・サービスの改善に役立つ
顧客アンケート、レビュー、カスタマーサポートのやりとりなど、企業が保有する多様な非構造データを生成AIで分析することで、改善すべき機能や不満の多いポイントを可視化できます。
これにより、製品開発やサービス向上における改善点の優先順位が明確になり、顧客の期待に沿ったアップデートがしやすくなるでしょう。
例えば、「ログインがわかりにくい」「サポートの返信が遅い」といった声が多数あった際には、AIがその傾向を抽出し、改善のヒントとして提示してくれます。
マーケティングやカスタマーサポートでの顧客体験向上
生成AIは、顧客データをもとに一人ひとりに最適化された広告文やメール文を自動生成できるため、パーソナライズされたマーケティングが実現しやすくなります。
さらに、チャットボットやFAQ自動応答など、カスタマーサポートの領域でも活用が進んでおり、ユーザーの問い合わせに対してスピーディかつ的確な対応が可能です。結果的に、顧客満足度やLTV(顧客生涯価値)の向上にも貢献するでしょう。
生成AIでデータ活用する上での3つの基礎知識
生成AIを効果的に活用するためには、理解すべき3つの「知識」があります。ここでは、「世界知識」「ドメイン知識」「特徴量」の知識の役割について解説します。
世界知識
生成AIは、大量のインターネット上の文章やデータを学習しており、一般的な常識や言葉の意味・文脈・背景情報などを理解しています。これが「世界知識」と呼ばれるもので、「AIの前提知識」として活用されます。
例えば、「売上が減る原因は?」と尋ねた場合に、経済情勢や競合、季節要因など、一般的に考えられる要素を出力するのは、この知識によるものです。
ドメイン知識
生成AIは、特定企業や業界の事情までは把握していません。こうした専門分野に特化した知識は「ドメイン知識」と呼ばれ、業務マニュアル、社内ルール、業界の商習慣などが該当します。
ドメイン知識をAIに組み込むためには、別途提供することが必要です。自社固有のデータやノウハウを取り入れることで、業界・専門分野特有の情報が補完され、生成AIの出力の精度を高められます。
特徴量(データに潜む知識)
生成AIのもう一つの重要な知識が、業務データから導き出される「特徴量」です。これは、数字や行動データの中に隠れた傾向やパターンのことで、AIはこの特徴をもとに予測や分類を行います。
例えば、「顧客の解約予測」を指示した場合、過去の行動履歴や利用頻度の変化といったデータから、可視化しにくい兆候を捉えて回答することが期待されます。
生成AIでデータ活用するやり方・手順
生成AIを活用したデータ分析を効果的に進めるためのやり方・手順は、次の通りです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1. データ整備と準備 | データのノイズ(不要な情報や誤差)を除去し、形式を統一するなど、AIが扱いやすい形に社内データを整理する |
| 2. 学習方法の選定 | 用途や目的に応じて、RAG(検索連携型)、ファインチューニング(追加学習)など適切なアプローチを選ぶ |
| 3. データのセキュリティとプライバシーの確保 | 個人情報や機密情報を扱う際は、暗号化やアクセス制限などで安全性を担保する |
| 4. 成果の評価とフィードバックの活用 | AIの出力結果に対して人がレビューし、改善ポイントを見つけて次回に反映させる |
| 5. 継続的な学習とモデルの更新 | 新しいデータや業務の変化に応じて、AIの学習内容やプロンプト(指示や質問)設計を定期的に見直す |
これらの手順を踏むことで、より効果的に生成AIを用いたデータ活用を進められます。
生成AIでデータ活用する際の注意点
生成AIを使ったデータ活用は多くの可能性を秘めていますが、一方で注意すべきポイントもゼロではありません。AIの特性や限界、データ管理の重要性を理解し、適切な対策を講じることが重要です。
ここでは、生成AIでデータ活用する際の4つの注意点についてわかりやすく解説します。
ハルシネーションへの対策が必要
ハルシネーションとは、生成AIが事実と異なる情報を、あたかも正確な情報かのように出力してしまう現象です。実際には存在しないデータや、誤った解釈を返すことがあります。
これはAIが与えられた情報をもとに推測や生成を行うため、避けられない面です。対策としては、出力内容を必ず人がチェックし、誤りを訂正・フィードバックすることが求められます。
出力の不安定さや数値処理の弱点を理解する
生成AIは自然言語での表現に優れていますが、出力のばらつきが生じ、同じ質問に対して結果が変わることがあります。
また、計算や複雑な数値処理は苦手な傾向もあるため、重要な数値分析には専用ツールや二重チェックを行い、AIの結果を鵜呑みにしないことが大切です。
セキュリティとプライバシーの管理徹底
社内データをAIに入力する際、個人情報や機密情報が第三者に漏れるリスクがある点には注意が必要です。
そのため、生成AIに機密情報や個人データを扱わせる場合は、暗号化やアクセス制限を徹底する必要があります。利用するシステムやクラウドサービスの安全性を確認し、社内ルールに沿った運用を心がけましょう。
データと人材の整備
生成AIでデータ活用するためには、データの整理やAIに関する専門知識を持つ人材の確保などの準備が必要です。データの質を保ちつつ、AIの特性を理解した運用体制を整えることで、生成AIの効果を最大化できます。
無料で試せる生成AIのデータ活用ツール
ChatGPT|OpenAI

引用:ChatGPT
ChatGPTは自然言語での質問への回答や、データ分析の補助ができるAIチャットボットです。「GPT-4.0」のバージョン以降では、CSVやExcelのデータを読み込んで解析することや、Pythonコードを自動生成してグラフを作成することが可能です。
2025年7月時点での最新バージョンは「GPT-4.5」となっており、前バージョンの「GPT-4.0」は一部機能に制限があるものの、無料でも利用できるため、初心者でも試しやすいでしょう。
Copilot in Excel|Microsoft

CopilotはMicrosoft 365に組み込まれたAIアシスタントであり、Excel上で自然な言葉を使って関数の作成やデータの要約、分析を行うことが可能です。
日常的な作業の自動化に役立ち、無料試用期間や教育機関向けの無償提供もあります。Excelユーザーにとっては便利なツールといえるでしょう。
Google Workspace with Gemini|Google

引用:Google Workspace with Gemini
GeminiはGoogleスプレッドシートと連携し、自然言語でのデータ操作や分析を可能にする生成AIです。
Google Workspaceのユーザーに向けて段階的に提供されており、一部機能を無料で試すことができます。Googleサービスを日常的に利用している方におすすめです。
まとめ
生成AIを活用したデータ分析は、企業や組織の成長に欠かせない重要な取り組みです。
データサイエンティストの人材不足が課題となる中、多くの企業が生成AIを用いて自社データを有効活用し、業務効率化や顧客満足度の向上を実現しています。すでにさまざまな業界で成功事例が増えているため、今こそ積極的に取り組むべき時といえるでしょう。
これまで蓄積してきた自社のデータやノウハウを、生成AIの力で新たな価値創出につなげてみてはいかがでしょうか。