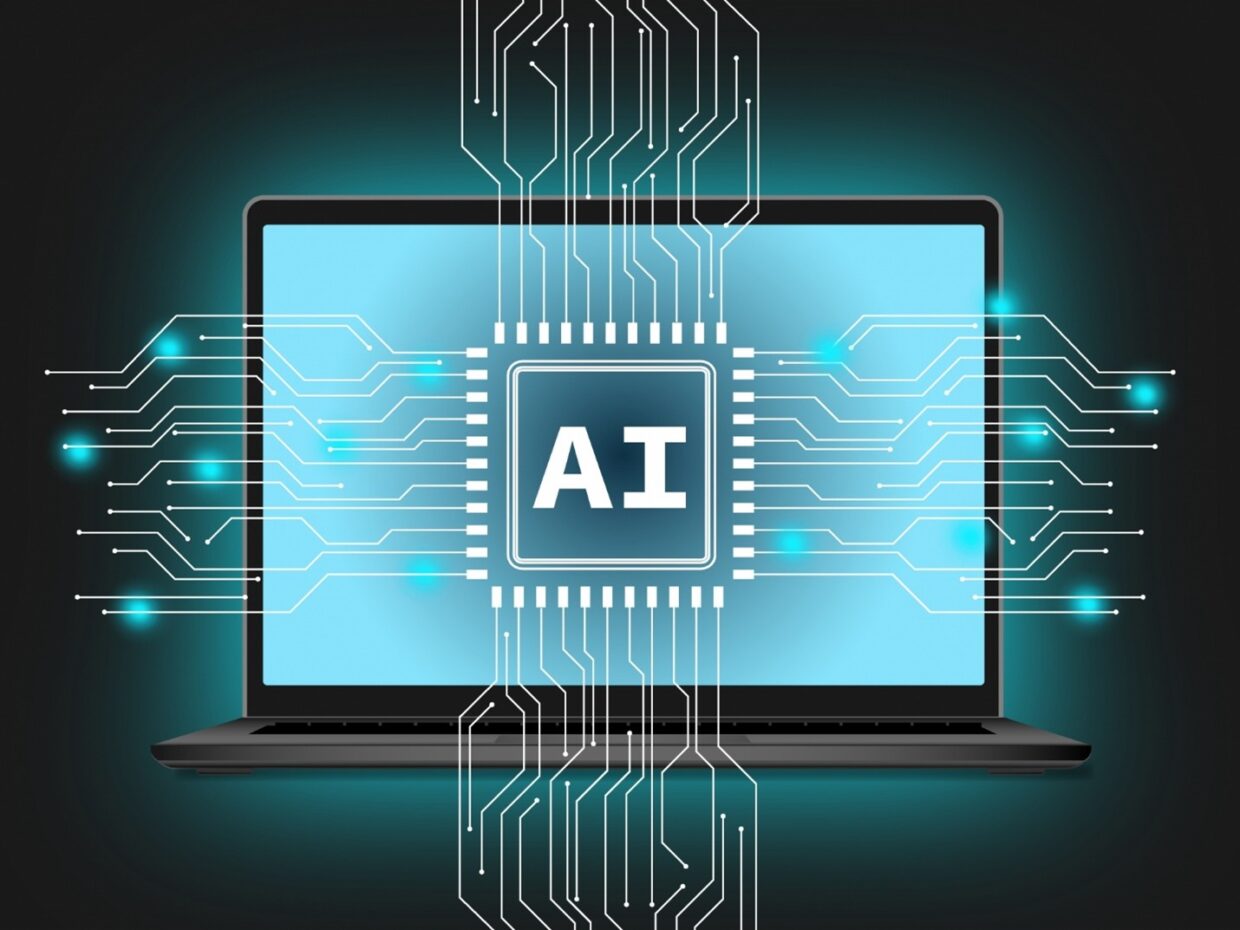
ChatGPTなどの生成AIの登場により、文章作成や情報検索などさまざまな業務が効率化できるようになりました。その一方で、与える指示文である「プロンプト」の書き方次第で、得られる回答の質が大きく変わることをご存知でしょうか。期待通りの成果を引き出すには、プロンプトの工夫が欠かせません。
この記事では、生成AIプロンプトの基本と上手な書き方のコツ、ビジネスシーン別の活用例をご紹介します。生成AIの性能を最大限に発揮できるプロンプトのポイントを押さえ、業務改善につなげましょう。
生成AIプロンプトとは
生成AIを使いこなすために欠かせないのが「プロンプト」です。まずは、プロンプトの基本的な役割と、なぜ出力品質に直結するのかを整理します。
プロンプトの定義と役割
「プロンプト」とは、ChatGPTのような生成AIに対してユーザーが入力する指示や質問のことです。生成AIにどのような出力を求めるかを伝えるもので、いわばオーダー表にあたります。プロンプトの内容如何で回答の方向性や詳細さが決まるため、とても大切な要素です。
明確で具体的なプロンプトであれば生成AIは能力を発揮しやすく、逆に曖昧なプロンプトでは的外れな回答や誤った情報が返ってくる可能性があります。
出力品質に直結する理由
プロンプトの良し悪しは、生成AIから得られる回答の品質に直結します。例えば、漠然と「カレーのレシピを教えて」と指示した場合、生成AIは一般的な情報しか提供できず、ユーザーの意図から外れた回答になるかもしれません。
ところが「夏野菜を使ったスープカレーの作り方を教えてください。大人向けのスパイシーな味にしたいです」といった具体的な指示にすれば、狙いに合った明確な回答が得られます。
このように、プロンプトの精度が高いほどAIは解釈に迷わず、正確で一貫性のあるアウトプットを返しやすくなります。逆に情報不足やあやふやな指示は、誤解による見当違いの答えや長すぎる説明につながりがちです。
生成AIプロンプトの書き方
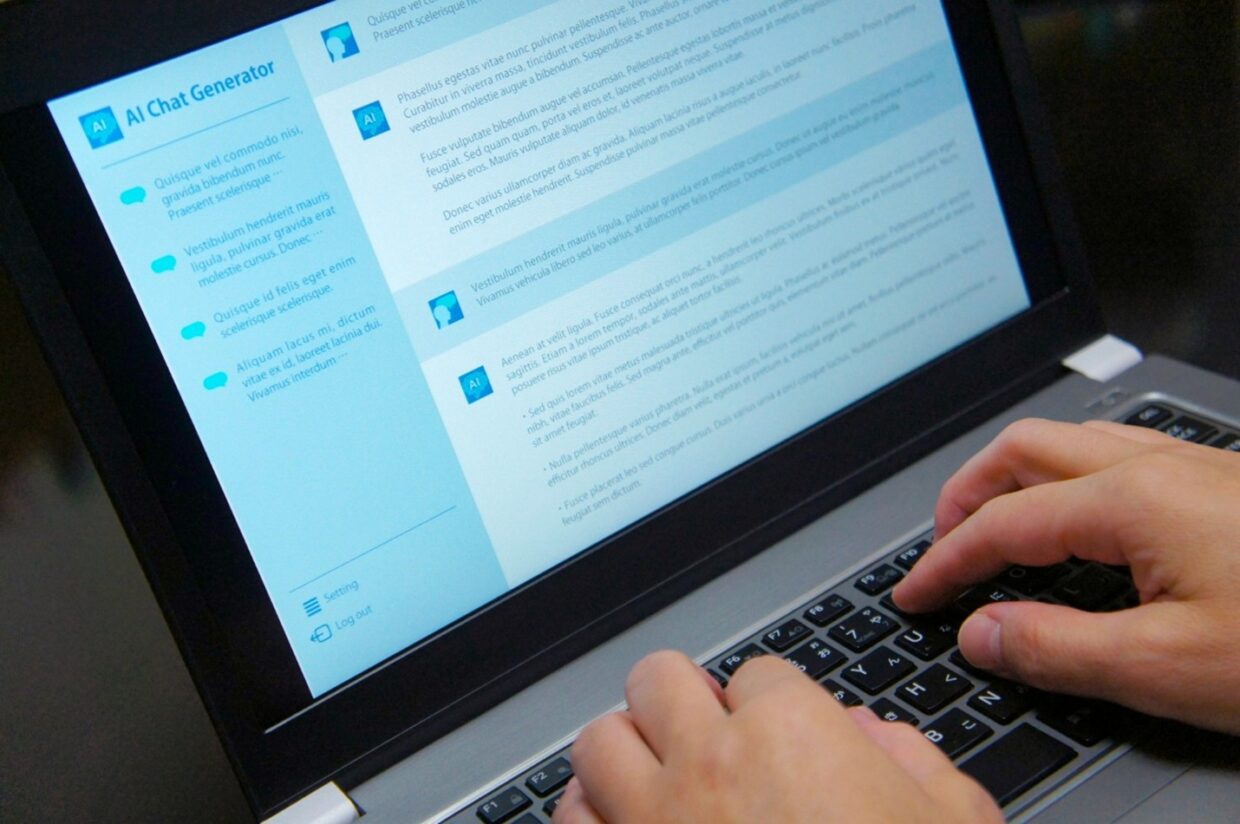
生成AIのプロンプト設計にはいくつかの原則があります。ここでは、実務で成果につながる具体的な書き方とコツを解説します。
ゴールを明確にする
まずは「何を得たいのか」を明確に定義しましょう。プロンプト作成時には、求めるコンテンツの種類や用途、対象読者をはっきりさせることが大切です。「文章を要約して欲しい」「顧客向けの提案書を書きたい」など目的を意識して指示することで、出力のブレが減り生成AIの回答も絞り込まれます。
例えば「高校生向けに環境問題を説明する文章が欲しい」と最初に伝えるだけで、生成AIは専門用語を避けた説明をしてくれるでしょう。ゴールを具体的に設定することで、プロンプト全体の方向性が定まり成果につながりやすくなります。
モデルに役割を与える
生成AIに回答者としての役割や口調を指定することも効果的です。「あなたは税理士です」「専門家として回答してください」のように前置きすることで、生成AIがそのキャラクターになりきって専門知識や適切な文体で回答してくれます。
例えば「あなたは経験豊富なビジネスコンサルタントです。企業の成長戦略についてアドバイスしてください」と役割を与えれば、より専門的で踏み込んだアドバイスが期待できます。また「カジュアルな口調で」「敬語で」など文体やトーンを指定することで、回答のスタイルもニーズに合わせて調整できます。
出力形式をテンプレートで指定する
回答の形式やレイアウトをテンプレートであらかじめ指定することで、実務で使いやすいアウトプットを得ることができます。例えば「箇条書きで答えてください」「表形式で結果を出力してください」のように求める形式を伝えると、情報が整理された形で提示されます。必要に応じてテンプレートや例をプロンプト内に示すのも有効です。
例えば、「以下のフォーマットで回答してください。」と書けば、その雛形に沿った回答が得られます。出力形式を指定することで、後から自分で整形し直す手間を省き、生成AIの回答をそのまま資料やメールに転用しやすくなるメリットがあります。
コンテキストを補足して曖昧さを減らす
プロンプトには背景情報や前提条件をできるだけ盛り込みましょう。質問の文脈や目的となる状況を伝えることで、生成AIはより正確に意図を汲み取ります。例えば「昨日の会議で決定した事項を踏まえて報告書の概要をまとめてください」のように、事前情報や制約を付記すると回答の精度が上がります。
特にビジネス用途では、自社の商品・サービス名・専門用語の定義などを与えることで、一般論ではなく自社に即した内容を出力させやすくなります。曖昧さを減らすために、「前提:○○」「条件:○○」といった形でコンテキストをプロンプト内に整理して書くのも効果的です。
出力を確認して修正を繰り返す
プロンプトは一度で完璧に仕上げることは難しく、出力を見ながら改善していくことが重要です。うまくいかないプロンプトには共通した課題があり、以下の点に注意すると精度を高められます。
- 曖昧な指示:主語や目的語を省略せず、具体的な数値や名称を盛り込む
- 情報の詰め込みすぎ:複数の要件は分割し、ステップごとに質問する
- 情報不足:背景や条件を補足し、不明点を残さない
まずは出力を確認し、必要に応じて修正を加えながら繰り返すことで、より正確で一貫性のある回答が得られます。
送信前にチェックリストで確認する
プロンプトを書いたら、送信する前にチェックリストで見直してみましょう。誤解を招く表現や漏れがないか、以下のポイントを確認します。
- 目的・成果物は明確に伝わっているか(誰に向けて何をしてほしいか)
- 前提情報や条件は必要十分に含まれているか
- 出力形式や文量の指定は適切か
- 曖昧な表現や主語の抜け漏れはないか
- 必要に応じて生成AIに役割を付与しているか
- 1回のプロンプトに要求を詰め込みすぎていないか
上記を満たしていれば、かなり品質の高いプロンプトと言えます。チェックリストを活用することでプロンプトの抜け漏れを防ぎ、安定した成果を得られるでしょう。テンプレート化しておけば毎回ゼロから考え直す手間も省けます。
【ビジネスシーン別】生成AIのプロンプト活用例

続いて、具体的なビジネスシーンごとに生成AIプロンプトの活用例を見てみましょう。生成AIを使えば、日々の業務で以下のようなサポートを得ることが可能です。
顧客対応メール
クレーム対応のメールや、お問い合わせへの回答メールを作成する場面です。定型文をそのまま送るのではなく、生成AIに状況に合った文面を考えてもらうことで、より丁寧で適切な返信が短時間で作れます。
例えば、商品不良の謝罪メールを書く場合は「宛先:取引先のお客様」「目的:納品不良に対する謝罪と代替品の提案」「トーン:丁寧かつ誠意が伝わるように」といった要素を盛り込んでプロンプトを作成します。実際のプロンプト例としては、次のようになります。
あなたはカスタマーサポート担当です。以下の条件に従って謝罪メールの草案を作成してください。
【宛先】取引先のお客様(企業)
【状況】納品製品に不具合。現在、社内で原因調査中。交換対応は可能。
【トーン】丁寧・誠実。責任の所在を断定しない。
【必須項目】件名/冒頭挨拶/事象の認識/現時点での対応(交換手配・再発防止検討)/今後の流れ(担当・目安日程)/連絡先
【禁止事項】未確認の原因断定、確約できない納期・補償の提示、不要な個人情報
【出力形式】見出し付き本文(300〜400字)
このようにプロンプトで宛先・目的・背景を明示すれば、生成AIはそれらを踏まえた自然な文章を生成してくれます。忙しい中でも顧客一人ひとりに合わせたメール対応が可能になり、対応品質の向上と時間短縮につながります。
長文要約(レポート・議事録)
分厚いレポートや会議の議事録を要約し、ポイントだけを掴みたい場面です。生成AIに文章要約を任せれば、短時間で要点だけを抽出できます。
プロンプトを作る際は、「元の文章」「要約の長さ」「要約の観点(視点)」を指定するのがコツです。例えば、社内報告書の要約なら次のようなプロンプトが考えられます。
あなたはビジネスアナリストです。以下の本文を要約してください。
【要約の用途】社内共有(意思決定の材料)
【観点】1) 結論 2) 根拠データ 3) 決定事項 4) 未決事項 5) 担当者と期限
【長さ】全体で300字以内+箇条書き5点以内
【厳守】本文にない内容は推測しない。曖昧な箇所は「不明点」として原文引用(20字以内)を添える。
【出力形式】見出し→箇条書き→最後にアクション項目(担当/期限)
【本文】<<<ここに対象テキスト>>>
このように役割(ビジネスアナリスト)と出力形式(箇条書き)、さらに要約項目数を指定することで、重要事項に絞り込まれた簡潔な要約が得られます。議事録の要約でも、「決定事項」「担当者と期限」を抜き出すよう指示すれば、会議後の共有資料作成が格段にスムーズになるでしょう。
企画アイデアの整理と展開
新規企画のアイデア出しや、ブレストで出た案を整理・肉付けしたい場面です。生成AIはアイデア発想や深掘りにも役立ちます。例えば、新商品企画のブレインストーミングであれば、生成AIに対して「マーケター」としての役割を与え、アイデア出しを手伝ってもらいます。
あなたはマーケティングの専門家です。○○業界向けの新製品アイデアを5つ提案してください。
【役割】マーケティング専門家
【観点】アイデアごとに以下を記載してください
1) ターゲット顧客(職種/規模/課題)
2) 提供価値と差別化ポイント(既存との違い)
3) 市場規模の簡易推定(前提を明記)
4) 実現性(技術・法規・コストを★5段階で評価)
5) 想定リスクと回避策
6) 直近2週間でできる検証手順(MVP内容/評価指標/合格基準)【禁止事項】
– 一般論やバズワードのみの記述
– 本文にないデータを「確定情報」と断定すること【出力形式】
– 各アイデアを表形式で整理
– 最後に上位2案を比較し、採用理由を150字程度で記載
このプロンプトではアイデア数(5つ)や知りたい観点(ターゲットと差別化)が明示されています。生成AIは指定した数のアイデアを順序立てて提案し、各案のポイントも整理してくれるでしょう。
また、既存のアイデアに肉付けしたい場合は、「このアイデアのメリット・デメリットを列挙してください」といった追加の質問をするのも有効です。生成AIの客観的な視点を借りることで、企画のブラッシュアップがスピーディーに行えます。
まとめ
生成AIの出力結果はプロンプト次第で良くも悪くも大きく変化します。だからこそ、プロンプトの質が成果を左右すると言っても過言ではありません。
この記事で紹介したように、ゴールの明確化、生成AIへの役割付与、形式指定といったコツを押さえておけば、必要十分な回答を引き出しやすくなります。プロンプト作りはコツがいる作業ですが、ポイントを意識すれば誰でもすぐに実践できます。ぜひ自分の業務シーンで試行し、生成AI活用の効果を実感してみてください。

