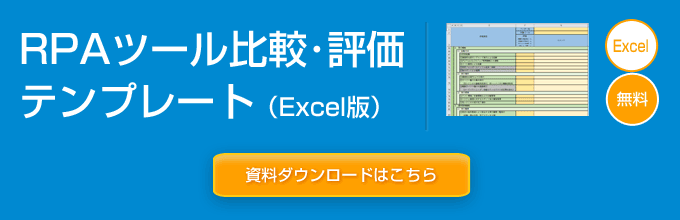2020年5月、日本のUiPath社より「Automation Cloud」の販売が開始されました。RPAツールの管理・最適化のための「Orchestrator」のクラウド版機能を使用することができます。より手軽に、高度な業務の自動化を叶えるAutomation Cloudの導入メリットを、インストール型RPAとクラウド型RPAの違いとあわせて詳しく解説します。
UiPath社のAutomation Cloudの特徴について
オフィスで人間が行ってきた単純作業を自動化し、業務の効率化を実現するRPA(Robotic Process Automation)ツール。Automation Cloudは、RPA市場でトップクラスのシェアを誇るUiPath社が提供するクラウドサービスです。同社の従来製品であり、RPAの管理や監視、最適化を行う「UiPath Orchestrator」が、クラウド上でより手軽に利用できるようになりました。
日本では、RPAといえばコンピューターやサーバーにツールをインストールする方法が主流でした。サーバーなど自社内でロボットを稼働させる場合はある程度機能をカスタマイズできるという利点がある一方で、インフラ構築のコストやアップデート対応が手動の可能性があるという点がボトルネックです。クラウド型のRPAは、初期構築のコストを抑え、インフラの構築や管理に割くリソースを業務の自動化に集中させることができるほか、リモートワークに対応しやすいのもメリットと言えます。
Automation Cloud独自のメリット

UiPath社のAutomation Cloudは、導入しやすく、安全かつ手軽に運用を続けやすいのが特長です。主な導入メリットは次の3点があります。
登録後すぐに導入できる
サーバーの構築が不要のため、サインアップをするだけですぐに利用可能です。インストール型RPAのようにパソコン内にデータをインストールしたり、セットアップをしたりする必要は一切ありません。
新たにインフラを構築する必要が無いため、登録から利用開始まで1分足らずという導入スピードで、テスト後、本稼働までに必要な期間も数日程度とスピーディーです。
信頼のセキュリティ体制
クラウド標準の認証プラットフォーム「Auth0」をサポート。MicrosoftやGoogleなどと連携しているシステムを活用することで、セキュリティ上強力な多段階認証を行うことも可能です。
また、クラウドでアプリケーションのセキュリティテストを実施しています。アプリケーションなどの脆弱性を特定する「Veracode」と、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO27001」の認証も受けているため、機密データの取り扱いも安心です。
状況に応じて拡張、拡大しやすい
必要な数のライセンスを取得できるため、事業の成長に合わせて容易に拡張、拡大が可能です。クラウドで一元管理できるため、開発したワークフローの社内共有やリリース・バージョンの管理も簡単にできます。
後から自動化する領域を拡大することもできるため、複数の自動化ツールを連携させて仕事をこなす「ハイパーオートメーション」を推し進めるのにも役立つでしょう。
インストール型と比較したクラウド型RPAのメリット

自社のPCなどへRPAツールをインストールしたうえで運用するインストール型RPAと比べると、Automation Cloudをはじめとするクラウド型RPAには、一般的に使い勝手や初期コストの面で次のようなメリットがあります。
同じ端末でほかの作業ができる
クラウド型のRPAは、ベンダー側のサーバー容量を使用して動作するため、端末の容量を占有しません。例えばRPAを稼働させながら他の作業をすることや、休日や平日の業務終了後に、端末の電源を落とした状態で稼働させておくことも可能です。
すぐに最新の機能が使用できる
インストール型のRPAは、手動で新しいバージョンをインストールする作業が必要です。しかしクラウド型であれば、自動で更新が行われます。製品の機能がバージョンアップされた際にも常に最新版を利用できるため、継続してワークフローを改善し続けることが可能です。
コストの削減が可能
ハードウェアの用意やインフラ構築が必要ないため、初期費用がかかりません。また、クラウド上でバージョンアップを済ませられるため、長期間継続して利用する場合の更新費用や新規購入の費用も抑えられます。
システムの保守・管理に継続的な人員を投入する必要もないため、人件費も削減可能です。
最後に
クラウド型の一種であるAutomation Cloudには様々なメリットがあります。初期構築の費用も抑えられるなど導入しやすいポイントもあり、効率化をスピーディーに推し進め、保守・管理の面でもストレスや負担を抑えることも可能です。
導入を検討している場合には、自社での懸念材料と比較検討したうえでまずはテスト導入してみるというのも一つの方法です。