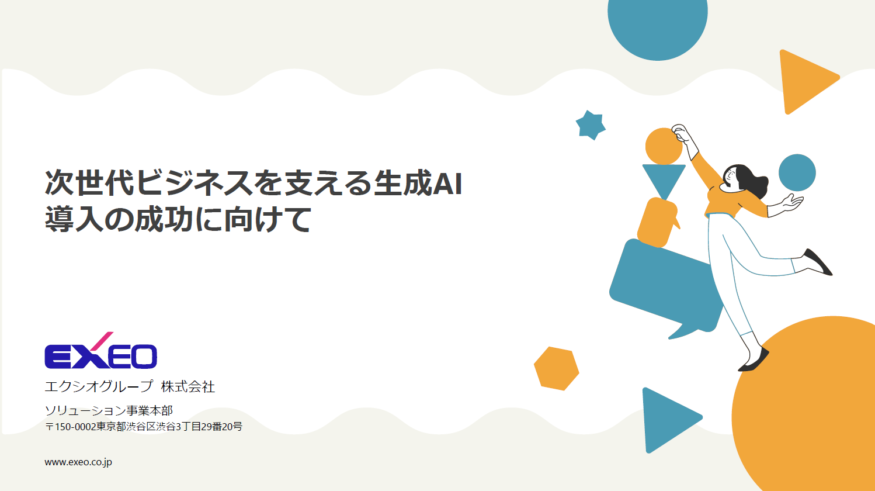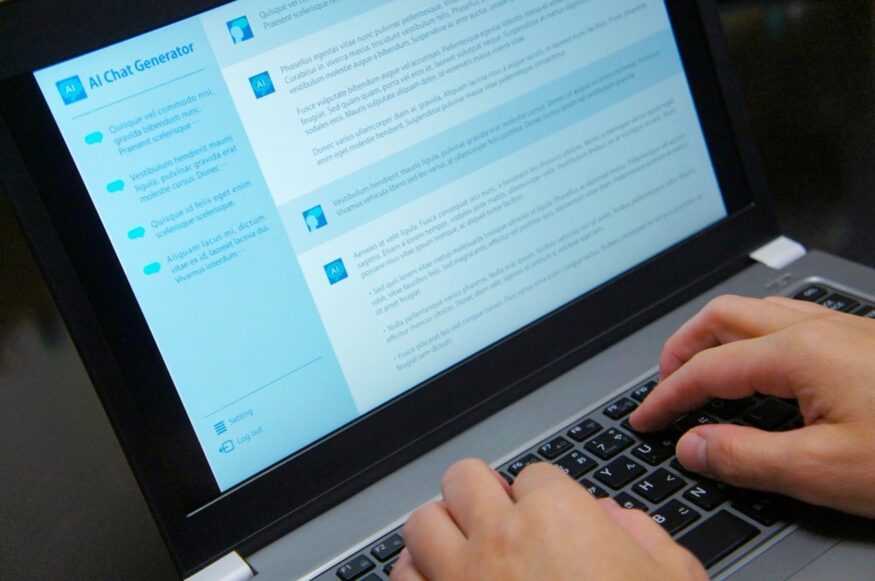
ChatGPTに代表される生成AIは、すでにビジネスや日常生活のさまざまな場面で活用されています。とはいえ、「興味はあるけれど使い方が分からない」「専門知識がないと難しそう」と感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、初心者の方に向けて生成AIの基本から具体的な使い方、活用できるシーン、注意すべきポイント、そしておすすめの生成AIサービスまでをわかりやすく解説します。日々の業務に生成AIを活用し効率化を図りたいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
1. 生成AIとは?初心者でも分かる基本解説
生成AI(Generative AI)とは、その名の通り「新しいコンテンツを生み出すAI」のことです。
従来のAIが「過去のデータから最適解を導く」ことを得意としていたのに対し、生成AIは文章や画像、音声、動画などのコンテンツをゼロから作り出せるのが大きな特徴です。
代表的なサービスには、文章作成が得意な「ChatGPT」や「Claude」、画像を描ける「Midjourney」や「Canva」などがあります。
初心者が生成AIを活用するうえでまず知っておきたいのは、生成AIには得意なことと不得意なことがあるという点です。
生成AIが得意なこと
- 文章の作成(ブログ記事やメール文面の作成、文章の要約、翻訳、アイデア出しなど)
- 画像やイラストの生成(広告素材、SNS用画像)
- コードの自動生成・エラーの修正支援
- 会話形式での質問回答や要約
生成AIが不得意なこと
- 100%正しい情報の保証
- 完全にオリジナルな作品保証
- 人間的な感情や属人的な判断を伴う意思決定
生成AIは便利なツールではあるものの、あくまで人が使いこなしてこそ真価を発揮します。
初心者の方は、まずは「AIがどこまでできるか」「どこから人間の判断が必要か」を理解しておくと安心です。
2. 生成AIの基本的な使い方とコツ

初心者が生成AIを活用するには、どういった手順を踏めば良いのでしょうか。アクセスや登録の手順、具体的な使い方の一例まで詳しく解説します。
登録・利用方法の例(ChatGPT)
生成AIの多くはブラウザ上で動作し、アカウントを作成すればすぐにでも利用可能です。
たとえばChatGPTの場合、登録から利用開始までの流れは以下の通りです。
- ChatGPT(https://chatgpt.com/)へアクセス
- 「無料でサインアップ」を選択
- アカウントを作成
- 利用開始
ちなみに、ChatGPTには無料版と有料版があり、以下のような違いがあります。
| 無料版 | 有料版(Plus) | |
|---|---|---|
| 料金 | $0/月 | $20/月(約3,000円) |
| メモリ機能(過去に入力・生成した情報を参照する機能) | ✗ | ◯ |
| 画像生成 | 制限あり(1日あたり3回まで) | 制限なし |
| Sora(動画生成機能) | ✗ | ◯ |
| Deep Research(高度な情報収集・分析・要約機能) | ひと月あたり5回まで | ひと月あたり25回まで |
| 文字数の制限(出力・入力) | 最大8,000トークン(3,000~7,000字程度) | 最大32,000トークン(15,000~28,000字程度) |
有料版はさまざまな制限が少なく動画生成機能にも対応しているメリットがありますが、ひと月に3,000円という金額は決して小さくありません。
そのため、生成AIを初めて利用するのであれば、まずは無料版で試してみるのがおすすめです。
生成AIの使い方と基本ステップ
1. 入力(プロンプトを書く)
生成AIでは、チャットのように質問や依頼内容を入力します。これを「プロンプト」とよびます。
プロンプトを入力する際のコツは、できるだけ具体的かつ明確に指示することです。
たとえば、旅行代理店が商品の説明文やキャッチコピーを生成するために以下のようなプロンプトを入力しても、内容が漠然としておりターゲットとなる顧客へのアピールにつながらない可能性もあります。
【悪いプロンプトの例】
「北海道2泊3日の旅行プランを紹介するキャッチコピーと説明文を書いてください」
そこで、プロンプトの作成時には「誰向けの商品か」「どんな魅力を伝えたいか」を具体的に書くことがポイントとなります。
【良いプロンプトの例】
「20代カップル向けの北海道2泊3日旅行プランを紹介する文章を書いてください。
みどころの◯◯と◯◯を記載し、ロマンチックさを強調。キャッチコピーは◯文字以内、説明文は◯文字以内」
2. AIが回答を生成
AIはプロンプトを読み取り、学習データに基づいてキャッチコピーと説明文を作成します。
キャッチコピー:
大自然とグルメを満喫する北海道カップル旅
説明文:
大雪山の雄大な景色を楽しみ、夜は札幌で海鮮を味わう2泊3日のプラン。
ロマンチックな夜景や温泉も盛り込み、大切な人との忘れられない思い出作りをお手伝いします。
数秒で結果が返ってくるため、まずはその内容を確認してみましょう。
一読して方向性が合っていれば問題ありませんが、もし表現が抽象的であれば次のステップでブラッシュアップします。
3. 再調整(追加の指示でブラッシュアップ)
生成された文章に不自然さがあったり、情報が不足しているようであれば目的や読者に合わせて調整します。
上記の生成結果に再調整を加えるとすれば、以下のような内容が挙げられるでしょう。
- もっと具体的な観光地名を入れてください(例:小樽運河、函館山)
- 価格感を示して「手が届く贅沢」を強調してください
- 最後に「お問い合わせはこちらへ」という行動喚起を追加してください
ブラッシュアップした内容は以下の通りです。
キャッチコピー:
小樽の街歩きと函館の夜景を楽しむ北海道2泊3日
説明文:
小樽運河のロマンチックな雰囲気を散策し、函館山から眺める夜景で特別な時間を演出。
札幌では新鮮な海鮮丼を堪能。1人あたり3万円台からのお手軽プランでプチ贅沢を楽しもう。
お問い合わせは当店スタッフまでお気軽にどうぞ。
プロンプトに配慮したとしても、一度の出力で満足のいく結果が得られるとは限りません。
そのような場合には、追加でプロンプトを入力し調整することで望み通りの回答に近づいていきます。
生成AIを活用するうえでは、一発で完成させるよりも、何度かのやりとりしながら調整していくイメージが大切です。
生成AIを活用できるビジネスシーン

生成AIは業務の効率化からアイデアの創出まで、さまざまなビジネスシーンで力を発揮します。ここでは、代表的な部門ごとに生成AIの活用イメージとプロンプト例を紹介します。
営業・マーケティング
営業やマーケティングの現場では、顧客対応や資料作成に多くの時間が割かれます。生成AIを導入することで、反応の高い提案文やコピーをスピーディーに作成できます。
活用例
- 営業メールやフォロー文の自動作成
- 広告キャッチコピーの案出し
- FAQの自動応答文章作成
プロンプト例
「新規顧客向けに、ITサービスの導入を提案する営業メールを書いてください。
文字数は300字以内で、専門用語は使わずに分かりやすく。」
「20代女性向けの旅行キャンペーン広告のキャッチコピーを5つ提案してください。」
広報
企業の広報担当者は、自社の商品・サービスを広く認知してもらうために情報発信のアイデアを求められます。生成AIを活用すればプレスリリースの下書きやSNSへの投稿文面などの作成が一気にスピードアップします。
活用例
- プレゼン資料の骨子作成
- プレスリリース文の下書き
- SNS投稿のアイデア生成
プロンプト例
「新商品『◯◯』の発表に合わせたプレスリリースの冒頭文を書いてください。
読み手はIT業界のメディア担当者です。」
「Instagramに投稿する旅行会社公式アカウント用のキャプションを考えてください。
テーマは『夏の北海道旅行』、絵文字を交えて100字以内で。」
クリエイティブ職
ライターやデザイナーなどのクリエイティブ職にとって、生成AIはアイデア出しのための心強いパートナーとなってくれます。たとえば、Webサイトに掲載する記事のたたき台やデザイン案なども素早く用意できます。
活用例
- 自社ブログに掲載する記事やコラムの下書き
- 広告バナーのデザイン案出し
- 動画やナレーションの台本作成
プロンプト例
「◯◯をテーマに、初心者向けブログ記事の導入文を150字で書いてください。」
「美容サロンのInstagram投稿用のデザイン案を作成してください。
ピンクとゴールドを基調にした高級感ある雰囲気で、中央に『秋のトリートメントキャンペーン』の文字を配置。」
「◯◯をテーマにした社内研修動画のナレーション台本を、イントロ部分だけ作成してください。」
生成AIの使い方で初心者が注意すべきポイント

生成AIは使い方を間違ってしまうと深刻なトラブルを引き起こしかねません。初心者が生成AIを活用する際、どのような点に注意しておく必要があるのでしょうか。
情報の正確性
生成AIが出力するコンテンツはもっともらしく見えても、必ずしも正確とは限りません。
たとえば、資料の作成時には市場データや統計データを掲載することも多いと思いますが、「日本のEC市場規模は〇兆円」「スマホの普及率〇%」などの数値は古いデータが用いられていたり、根拠不明な数値が記載されていることも。
ほかにも、最新のニュースや法律関連などの情報は誤った内容が記載されている可能性があるため、生成AIが出力した内容は鵜呑みにせず最新の市場調査レポートや公的機関の情報などを照合するようにしましょう。
著作権・利用規約の確認
生成AIが作ったコンテンツは膨大な学習データに基づいて生成されています。悪意はなかったとしても、生成された文章や画像が他人の著作物と酷似していると模倣と捉えられるリスクもあるため、コンテンツの独自性や権利関係には注意が必要です。
また、生成AIのサービスによっては商用利用が許可されていないものもあるため、素材をそのまま利用する場合にはサービスごとの利用規約を確認しておきましょう。
個人情報を入力しない
生成AIに入力した情報はサービス提供者に送信され、学習データとして活用されることがあります。そのため、生成AIに氏名や住所、電話番号などの個人情報を入力すると情報漏えいのリスクが高まります。
業務で生成AIを活用する際には、個人情報はもちろんのこと機密情報をプロンプトに入力しないよう心がけましょう。
生成AIに依存しすぎない
生成AIで出力されたコンテンツをそのまま用いてしまうと、不自然な表現や言い回しが気になったり、独自性が低く機械的な内容に捉えられるおそれもあるでしょう。
生成AIはあくまで“たたき台”や補助ツールとして活用し、信頼性やオリジナリティを担保するためにも人の目による確認や編集を心がける必要があります。
初心者におすすめの生成AIサービス
生成AIについて調べるとさまざまなサービスが検索でヒットし、どれを選べば良いのか迷ってしまう方も多いはずです。そこで、初心者でも安心して利用できる生成AIを、文章生成・画像生成・動画生成の3つのジャンルに分けてご紹介します。
文章生成AI
【ChatGPT】
OpenAIの「ChatGPT」は生成AIの代名詞的存在で、1週間あたりのユーザー数は7億人以上を誇ります。会話形式で自然な文章を生み出せるのが特徴で、メール文や記事の下書き、長文の要約、翻訳など幅広い用途に対応。無料版から始められる手軽さも魅力で、有料プランではさらに精度の高い長文生成や高度なリサーチにも対応可能です。
【Claude】
「Claude」は長文生成や要約に強みを持つ生成AIです。大量のテキストを読み取り、文脈を踏まえたわかりやすい文章を生成できるため、レポートや企画書の下書きなどに最適。自然で丁寧な表現が得意なため、ビジネス文書にも活用しやすい点が特長です。
画像生成AI
【Canva】
「Canva」は初心者に最も使いやすいデザインツールのひとつで、テキストで指示するだけでイメージ画像を生成できる機能を備えています。作成した画像はそのままテンプレート編集が可能で、SNS投稿用のデザインや広告バナーを直感的に仕上げられるのが大きな魅力。デザイン経験がなくても、すぐに実用的な素材を作れる点が強みです。
【Midjourney】
「Midjourney」はアート性の高い画像に強みを持つ生成AIです。テキストによるプロンプトで写真風のリアルなイメージから幻想的なイラストまで幅広く生成できるため、クリエイティブ系の仕事やSNSでの差別化を図りたい方など、特に美しいビジュアルを求める人に人気があります。
動画生成AI
【Runway Gen-2】
動画生成AIの代表格で、テキストや画像から数秒の動画を自動生成できます。映像編集の知識がなくても直感的に操作でき、プロモーション動画やプレゼン用の背景映像などを短時間で制作可能。
映像のスタイルや雰囲気を細かく調整できるため、ビジネスシーンからクリエイティブ制作まで幅広く活用されています。
【Veo 3】
「Veo 3」はGoogleが開発した次世代の動画生成AIです。テキストによるプロンプトから最長8秒間の音声付き動画を生成できるのが特長ですが、Veo 3を利用するためには有料のGoogle AI ProプランまたはGoogle AI Ultraプランへの加入が必須です。
生成AIは初心者でも簡単!まずは使ってみよう

生成AIはプログラミングなどの専門的な知識が不要で、初心者でも気軽に使えるツールです。まずはメール文や社内ブログの導入文、簡単な画像生成など、身近な用途から試してみることが第一歩になります。
実際に使っていく中で「日々の業務のどこに役立つのか」を意識してみると活用の幅がさらに広がり、業務効率化や生産性の向上につながっていくでしょう。
生成AIは日々進化を続けており、できることの幅もますます広がっています。だからこそ、早めに触れて慣れておくことで生成AIの新たな可能性が見つかり、頼れるパートナーとして